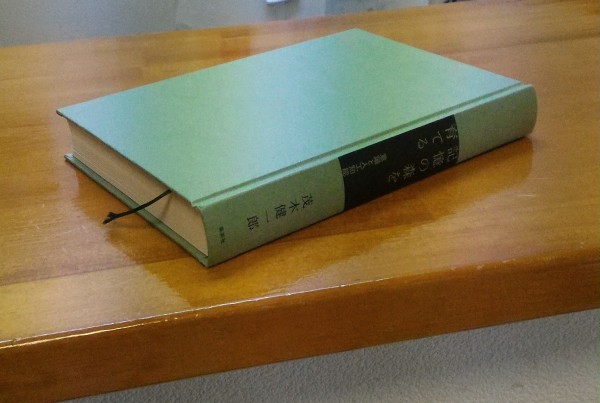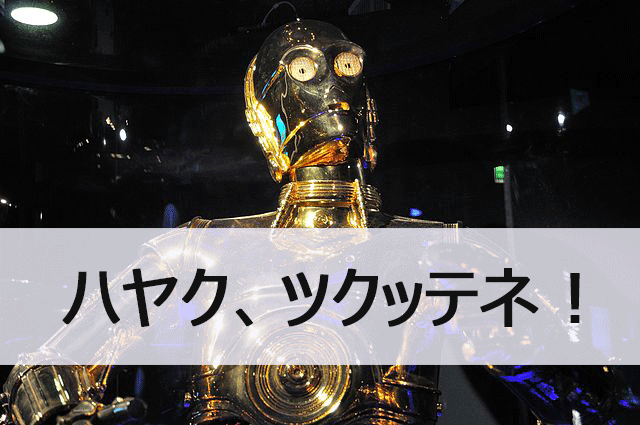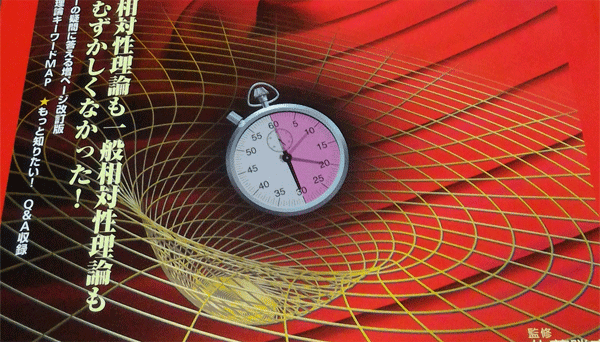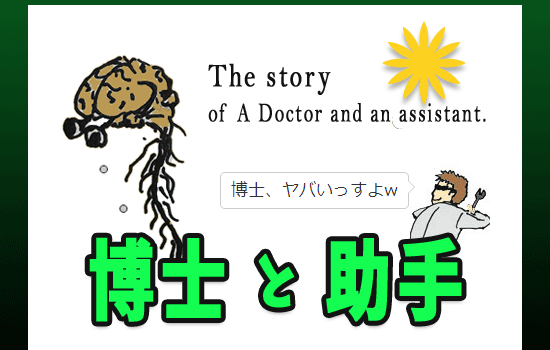スポンサーリンク
茂木健一郎とモギケン
茂木健一郎さんの著作「記憶の森を育てる」を読みました。
茂木さんって、TVではバラエティ番組用脳科学者モギケンに仕立て上げられています。
もしかしたらご本人も派手な衣装に身を包んだそのキャラクターを楽しんでおられるのかも知れませんが。(笑)
彼の著作を読むと、TVでの印象とは違った脳科学者としての硬派な一面に触れることができます。
僕はTVでモギケンを見るよりも先に、脳科学者・茂木健一郎の著作を何冊か読んでいたので、TVでご本人を見て正直ちょっとガッカリしました(茂木さん、ごめんなさいw)。
というのも茂木さんの著書には、脳科学という大いなる謎に挑む専門家としての知見、思い、その等身大の姿が、記されています。
それらを読んで、彼は素晴らしい研究者であり哲学者だなと感じるわけです。
ところがTVを見ると、「お勉強ができるようになるには?」とか「人間関係がうまくいくには?」とかっていういかにもお茶の間に受けそうな、言葉を選ばずに言えば、しょうもない話を脳科学者の見地から語っておられるわけです。
そんなの脳科学じゃないでしょと。
茂木さんが生涯を賭けて研究しているクオリアの謎というのはそんな低俗な話じゃないでしょと。
彼の著作のいくつかを見ると、「意識」とは何かという崇高な謎、その高みへ向けて懸命に手を伸ばしている本もあれば、逆に、世間一般へ向けたいかにも商業的な本もあります。
だいたいタイトルを見れば、どっちを向いて書いた本かはわかります。(笑)
しかしまあ安心して下さい。この「記憶の森を育てる」に関しては、当然、前者です。モギケンとしてではなく、脳科学者・茂木健一郎によるおそらく入魂の一冊です。
僭越ながら、その感想文を記したいと思います。
スポンサーリンク
オーバーフローモデル
視覚、聴覚、嗅覚、味覚、さらには体中に張り巡らされた触覚(温度覚・痛覚)は、常に脳へと何らかの信号を入力しています。
その全ての信号はまさに同時並行的に脳へと入力されています。
すれ違う人の顔、建物の色や形状、看板の文字、遠くの山、自動車のエンジン音、人の話し声、漂う空気の匂い、風が皮膚に当たる感覚、地面を踏みしめる足の裏の感覚、腰の痛み、暑さ、寒さ、空腹感あるいは満腹感、それはもうとてつもない容量です。
「意識」はその入力情報の全てを同時に知覚することはとてもできません。
意識的に注意をむけた話し声、あるいは自然と目に飛び込んで来た看板の絵、あるいは急激に襲われる腹痛など、能動的にせよ受動的にせよ、その全ての入力情報の中から取捨選択した感覚だけ(一つだけというわけではない)が意識に上り、感じられます。
脳の処理能力は有限なので、とても処理しきれない量の入力情報がダダ漏れの源泉かけ流し状態です。もちろんそのほとんどは認知もされず記憶にも残りません。
その際、脳内は、物理的オーバーフロー状態と言える状態になっています。
しかし、脳はその入力情報の大部分をスルーしているようで、実は、それらをある種の情報としてまとめあげ、認知し、記憶に留めています。
例えば、何気なく街を歩けば、特に注意して見たわけでなくても、その情景はなんとなく記憶に残るものです。
建物が多かったか?それとも遠くの景色まで見渡せていたのか?人通りが多かったか少なかったか?お店が多く並んでいたか?緑が多かったか?歩道は広かったか?ウォーキングに適した道だったか?好きか?嫌いか?
そんな風に、大量に浴びせられた入力情報の全てを記憶してはいないのに、脳はそれらの雑多な情報から大ざっぱな認知を立ち上げることができます。
この大ざっぱな認知を概略認知と呼び、概略認知を獲得しうるメカニズムを特に現象学的オーバーフローと呼んでいます。
現象学的オーバーフローは、脳に大量に入力された情報を、処理しきれないからといって単に無視するのではなく、その細部は捨て去りつつも統合的に認識する為の仕組みと言えると思います。
溢れるほどに入力される情報を有効利用しているわけです。
外界の情報をそのような形で認知できるというのは、自然界の生存競争において大きなアドバンテージになるのは言うまでもありません。
生命の進化の過程で、物理的オーバーフローに対応し適応する形で、脳が現象学的オーバーフローと呼ばれるメカニズムを獲得したことが「意識」の起源なのではないかという、「意識の進化のオーバーフローモデル」を茂木先生は提唱しています。
もしかしたら、脳という器官自体が物理的オーバーフローに適応しようとした結果なのかも知れません。
というような解釈で、茂木先生、間違っていませんでしょうか?
科学かつ哲学かつ文学
以上のような「意識」の仕組みとしての現象学的オーバーフローと概略認知について、掘り下げて書かれているのが第一章です。
第二章は、茂木さん自身が様々な場所で体験した出来事、その時の思いやその記憶について、エッセイ調で書かれています。
第三章では、意識と人工知能の違いや、人工知能の危険性など、様々な視点から今巷を賑わしている人工知能について茂木さんの思いが書かれています。
本書の楽しみは最先端の脳科学に触れるということだけではありません。
茂木さんの文章は、科学的でもあり哲学的でもありながら、その端々に文学的あるいは詩的な味わいも感じられ、独特な世界観があります。
非常に味わい深いです。中でも僕が特に気に入ったところを抜粋してご紹介したいと思います。
ニーチェの著書に登場する、「神は死んだ」と叫ぶ「狂人」のエピソードを紹介しながら、「神」と同型の存在とも言える「自由意志」について語った以下の一節。
自由意志は、一つの、強固ではあるが、因果的な根拠を持たぬ「幻想」に過ぎない。自由意志がもしあるとすれば、それは、この宇宙に対する「私」という「外部」からの介入ということになる。そのような外部性を、現代の科学的世界観は、許容しない。自由意志や、その倫理的帰趨に関心を払う「神」は、そのような「幻想」の中にだけ存在する。
物理的因果法則に従って発展するこの宇宙に対して、私たちの持つ「自由意志」を「外部からの介入」と表現している点が非常に面白いと思います。
そして、そんな外部から手を加えるような行為を現代の科学的世界観は決して許容しない。と自由意志の存在を(いわゆる神の存在と共に)ばっさりと斬り捨てています。
しかしながら、宇宙がどんどん無機質な数式に置き換えられていくその現実を認めつつも、その数式はhowに対する答えにはなり得ても決してwhyに対する答えとはなり得ないこと、そして「今、ここ」の重みを引き受ける数式は決して存在しないこと、といった現代科学の欠陥から逆説的に、「今、ここ」という絶対的存在(それと同型と言える「神」の存在)を導き、反「狂人」を呼び起こす。
ニーチェが生みだした狂人が叫んだように、本当に「神は死んだ」のであれば、私たちの「意識」もまた死ななくてはならない。逆に、「意識」がもし存在するならば、「神」もまた存在しなければならない。「意識」と「神」は、宇宙の存在論的重さへのかかわり方において、同じ場所を占めている。
矛盾しているようで、むしろその矛盾にこそ価値を見出す哲学的思考と文学的表現の職人芸。
ごちそうさまです。
そして「現象学的オーバーフロー」という科学理論までもを、文学に結び付けるその思考の縦横無尽。
「今、ここ」の豊穣をすべては残すことができないからこそ、私たちの脳は、その最も重要なエッセンスを、「記憶の森」の中に残そうとする。それは、もともとは、進化の過程で生き延びると言う適応から要請されたメカニズムであったが、結果として、文学を始めとするさまざまな芸術を花咲かせることとなった。
本書「記憶の森を育てる」は、脳科学者・茂木健一郎が育んできた記憶の森に根付いた一本の大木のように、あるいは一輪の花のように感じました。
脳科学に興味のある方はぜひご覧になって下さい。